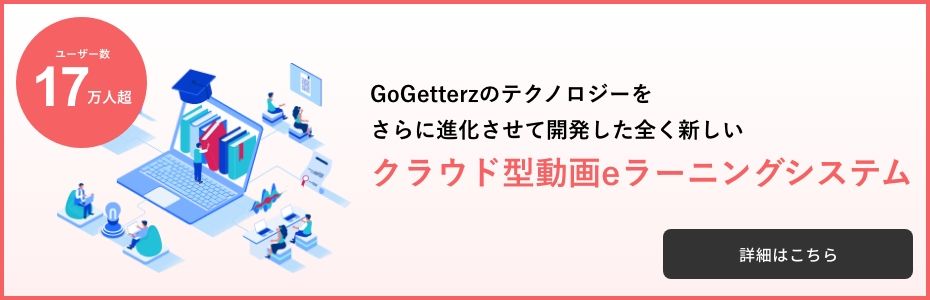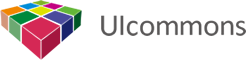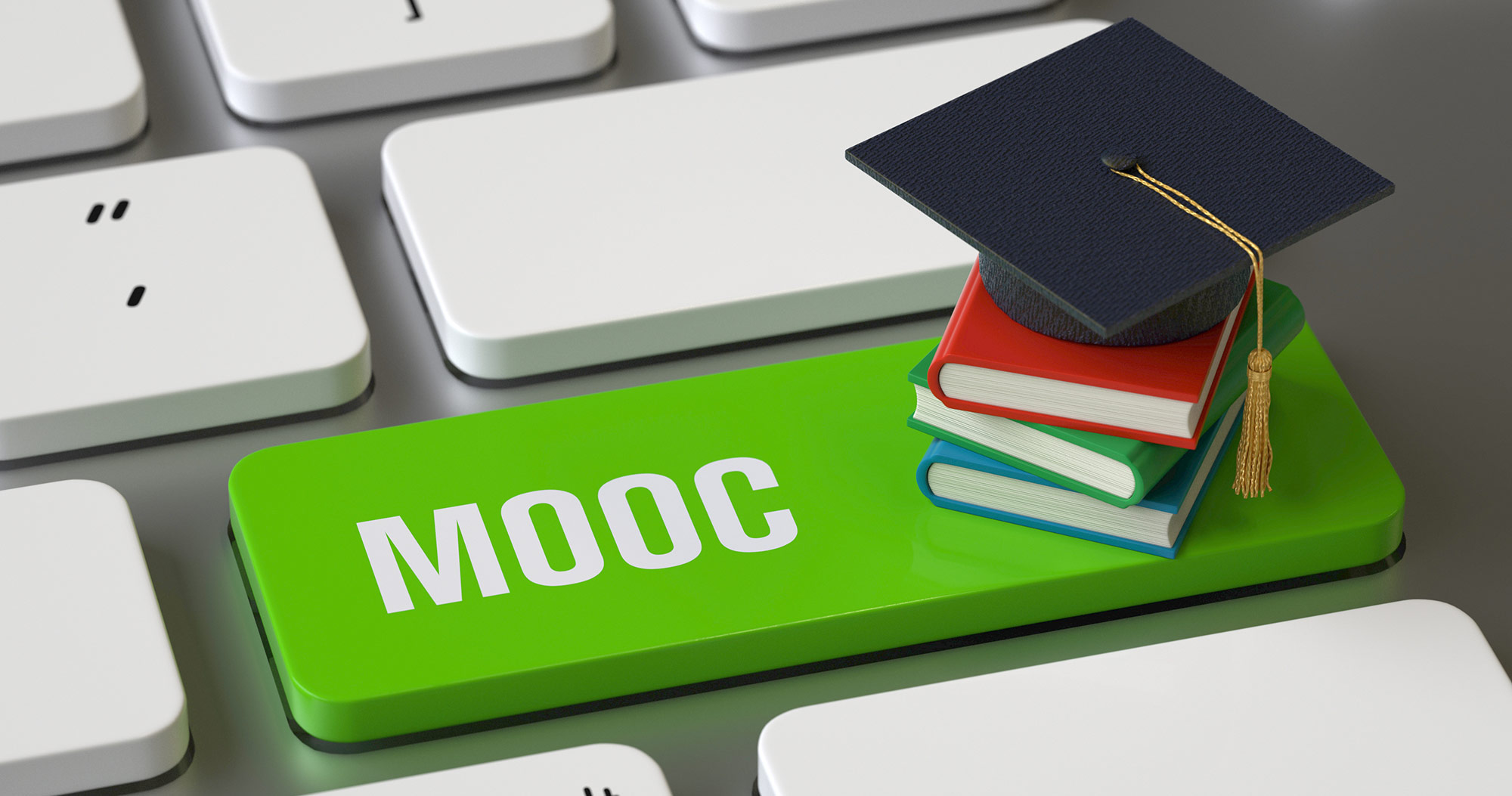
日本でもMOOC(MOOCs)の存在への認知が進み、2013年には日本版MOOCであるJMOOC(ジェイムーク)を普及・拡大するために「日本オープンオンライン教育推進協議会」が設立されました。
「MOOC(MOOCs)とは~さまざまなオンライン学習~」では、MOOC(MOOCs)とは何かについて基本的な情報をお伝えしました。
本コラムでは、もう少しMOOC(MOOCs)を掘り下げ、MOOC(MOOCs)のメリットは何か、逆にデメリットはないのか、MOOC(MOOCs)が抱える課題とは?といったテーマについてご紹介します。
MOOC(MOOCs)のメリット・デメリット
まずは、MOOC(MOOCs)のメリットから見ていきましょう。
1. MOOC(MOOCs)のメリット
MOOC(MOOCs)のメリットとして、「誰でも受講できる」「無料でハイレベルな講座を受講できる」を挙げることができます。
誰でも受講できる
MOOC(MOOCs)には入学テストのようなものがあるわけではなく、受講料があるわけでもありません。また、年齢制限などもありません。
このため、受講したい人は誰でも受講して学びたい内容を学ぶことができる点がMOOC(MOOCs)の最大のメリットです。
また、居住地域も制限されないため、どこに住んでいても受講できます。たとえば、日本にいながらにして米国の大学の講座を受講することも可能です。
講座は基本的に録画されているため、受講の時間帯も自由です。
無料でハイレベルな講座を受講できる
先ほどもお伝えしましたが、MOOC(MOOCs)の講座は基本的に無料で受講できます(一部、有料の講座があったり、修了証の発行が有料であったりします)。
しかも、講座を提供しているのは国内外のハイレベルな大学や業界を牽引する大企業など。最先端の内容を学ぶことができます。
また、海外の講座を受講する場合、言葉の壁がハードルになることがありますが、MOOC(MOOCs)ではさまざまな国からの受講者が想定されているため、受講中に日本語字幕を表示させることができる講座もあります。
2. MOOC(MOOCs)のデメリット
一方、MOOC(MOOCs)のデメリットは「モチベーションの維持が難しい」の一点に尽きます。
モチベーションの維持が難しい
MOOC(MOOCs)は、基本的に自宅などで自分一人で受講し、一人で課題に取り組んでいくスタイルで学習を進めていくことになります。通常の学校のようにほかの受講者からの刺激を受けにくく、講師との質疑応答などもしづらく、一方的に講義を受けることになります。
こうした双方向性の学習がしづらいことから、数週間から数ヵ月間にわたる受講期間、ずっとモチベーションを維持することが難しい傾向にあります。
受講料が無料であることも手伝って、途中で受講をやめてしまう人が多く、最後まで受講し修了する受講者は10人に1人とも言われています。
MOOC(MOOCs)に期待される効果とは
MOOC(MOOCs)には、受講者視点でのメリット・デメリット以外にも、教育に関するさまざまな課題解消が期待されています。
1. 専門性が高く進歩の速い分野へのキャッチアップ
たとえば、医療や情報セキュリティといった専門性が高く、かつ進歩の早い分野に関する知識は、いちど身につけても時間の経過とともに技術が進歩するため、陳腐化してしまうおそれがあります。これらの分野に関わる実務者は、最新の知識をキャッチアップし続けなければなりません。
しかし、多忙な社会人が学習のために割ける時間は限られています。
そこで、インターネット環境さえあればどこからでも講義に参加できるMOOC(MOOCs)の活用が期待されているのです。
また、分野としては、法律が改正されることで大きく実務面が変わってくるような法務や税務、財務といったところでも同様の活用が期待できます。
2. 生涯教育の醸成
学習に対するモチベーションは、実務に活かすためだけにあるものではありません。いくつになっても知的好奇心は持っていたいもの。厚生労働省も、生涯教育は個人の心の豊かさや生きがいにもつながるものとして推奨しています。
とはいえ、大学や専門学校へ通うためにはそれなりの学費と時間がかかります。
その点、MOOC(MOOCs)を活用すれば、インターネット環境さえあれば高度な教育がほぼ無料で受けられるようになります。
さまざまなジャンルの幅広い講座が用意されているMOOC(MOOCs)は、生涯学習に打ってつけだと言えます。
3. 高校と大学の教育の連携
前項は社会人以降のライフステージに立つ人を対象とした議論でしたが、逆に大学入学前の高校生をターゲットとしたMOOC(MOOCs)を考えると、高校と大学の教育の連携が可能になってきます。
実際に日本のMOOC(MOOCs)のひとつ「gacco」では、高校生向けの講座が用意されています。
たとえば、滋賀大学が提供する「高校生のためのデータサイエンス入門」を見ると、本格的なビッグデータを扱うわけではないものの、数学Ⅰの「データの分析」で習う手法では、高校生にも身近なスマートフォンやコンビニを取り上げつつ、データから有用な情報を引き出す方法について解説し、未来のデータサイエンティスト育成につなげています。
MOOC(MOOCs)の課題
上でご紹介したような受講者側のデメリットのほか、MOOC(MOOCs)そのものが抱える課題には次のようなものがあり、今後の普及のためには解消の必要がありそうです。
1. ビジネスモデルとしてどう収益をあげるか
利用者としては無料で受講できる点が大きなメリットのMOOC(MOOCs)ですが、講義を提供する側が収益をあげられないと、どんどん撤退してしまい、MOOC(MOOCs)そのものが成立しなくなり、いずれは利用できなくなってしまいます。
現状では、有料講座の提供や修了証発行時の手数料、オンラインコミュニティの利用料などで収益をあげていますが、十分な売上のあるところはそう多くはないでしょう。今後、考えられる収益源としては、優秀な受講者を企業に紹介するリクルーティングなどがあります。
2. 修了率の低さ
「MOOC(MOOCs)のデメリット」でお伝えした内容とも重なりますが、自宅などで一人で講座を受講し、修了まで継続していくには数週間から数ヵ月間、モチベーションを維持していく必要があります。
ただ、実際に継続できる人は少なく、修了者は受講者全体の1割程度ともいわれています。
修了率の低さは、MOOC(MOOCs)そのものの価値を左右してしまいますし、講座を提供する大学や企業の収益も見込めなくなってしまい、MOOC(MOOCs)存続が危ぶまれる重大な課題となります。
海外のMOOC(MOOCs)では、修了率を上げるために、通学で学ぶ学校と同様に受講者同士のコミュニティでの議論や、教師との質疑応答の場を設けている講座や、レポート課題を受講者が相互にチェックし合うピアレポートの制度を導入している講座があります。
まとめ
以上、MOOC(MOOCs)のメリットと課題についてご紹介しました。
海外では2006年頃からMOOC(MOOCs)の講座が開講されて認知度も高いですが、日本ではまだ実際に受講経験がある方はそう多くはありません。
上でご紹介したように、MOOC(MOOCs)にはまだまだ課題もあります。今後、解消への取り組みは必要ですが、世界的な流れを考えると日本でも広く普及していくことになりそうです。
eラーニングの概要・種類について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
eラーニングシステム11選をわかりやすく比較!〜メリットやデメリットまでご紹介~

クラウド型動画eラーニングシステム
UIshare(ユーアイシェア)のサービス資料
圧倒的な低コスト、充実したサポート体制で、社員教育・社内情報共有・パートナーへの情報共有・動画 e ラーニング・eラーニング販売など様々なシーンでご利⽤いただけます。