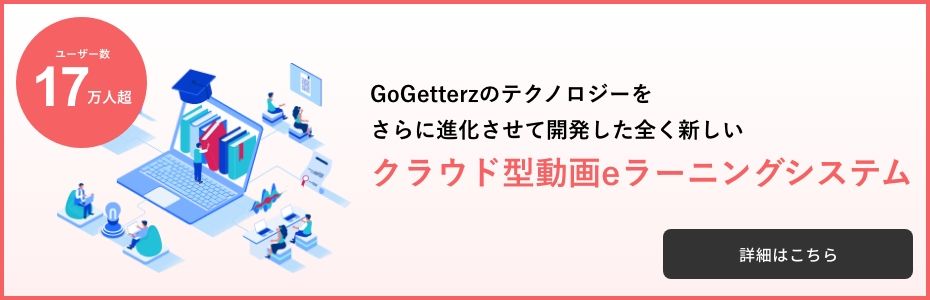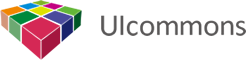感染症の蔓延対策や働き方改革、子育て世代のワークライフバランスを考えるなかで、テレワークの導入が積極的に推進されるようになりました。
テレワーク(tele:離れた場所、work:働く)とは情報通信技術(ICT:Information and Communication Technology)を活用した、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を指す言葉です。在宅勤務や外出先におけるモバイルワーク、サテライトオフィスへの勤務など、いくつかの形態があります。
テレワーク導入に踏み切る企業は数多くありますが、そのすべてが成功しているわけではありません。中には思うような成果が得られず、元通りの勤務形態に戻す企業もあります。では成功する企業と失敗する企業の違いは、どこにあるのでしょうか?実は「業務の見える化」にかかっているのです。
業務の見える化とは
「業務の見える化」とは、作業手順や業務プロセスの明確なマニュアルを用意し、業務の問題点も把握できるようにすることを指します。それらに沿って作業を進めれば、ある一定の成果が得られるようなマニュアルです。
「見える化」の対義語ともいえる言葉が「属人化」です。特定の人しか業務のプロセスが把握できておらず、他に誰も手出しができないような状況を指します。勤務年数が長いスタッフだけが把握できていて、他のスタッフから進捗状況がほとんどつかめない業務内容がある企業も多いのではないでしょうか。
何らかのプロセスが属人化してしまうと進捗状況や結果のチェックが行き届かなくなり、生産性が大きく低下します。高度な技術や経営判断を必要とされるごく一部の業務を除き、属人化は業務改善の妨げになる現象です。
テレワークを導入しない企業の多くは、「テレワークに適した仕事がないから」という理由を挙げますが、実はテレワークに適していない仕事はそれほど多くありません。
「平成29年度テレワーク人口実態調査」(国土交通省)によると、職種別で見た場合、管理職や営業、研究職など、個人の裁量が大きい職種ではテレワークの普及が進んでいることがわかります。一方で販売や生産工程従事者、運輸・清掃・包装等従事者であっても、少ないながらテレワークが導入されています。
大枠でみて「あの人の仕事はテレワークだとできないから」と切り捨てるのではなく、まずは仕事を細分化して見える化しましょう。その中にはテレワークに適した業務内容も含まれているはずです。
マニュアル化の必要性
テレワークを成功させるには、「業務の見える化」が欠かせません。やるべき仕事が見えていない状態だと、テレワークで働いた成果が目指すべきラインに達しているかどうか判断できないためです。そのため、テレワークを導入したいなら業務内容を一度すべて洗い出し、マニュアル化していきましょう。
日本では、仕事内容を明確化してその職務に応じた賃金を支払うアメリカのような「ジョブ型」の雇用形態ではなく、職務範囲を明確に定めない「メンバーシップ型」の雇用形態が一般的です。
そのため個人のこなすべき仕事の範囲が判断しにくく、定められた仕事以外を業務時間内についでにこなすということがしにくいテレワークが、普及しにくかったという背景があります。多くの企業では個人の負うべき責任の範囲も明確化されていません。
賃金形態も職務内容そのものではなく、勤務時間に応じて支払われます。そのため、勤務時間を明確に測定しにくいテレワークは日本ではこれまであまり普及しませんでした。
マニュアル化のプロセスでは業務内容を明確に定義し、業務手順も可視化することになります。このプロセスは地道で時間がかかる作業ですが、テレワーク導入の下地になるだけでなく、業務改善を進める意味でもとても意味がある作業です。
「個人の判断に任せる範囲が広く、誰もができる仕事ではない」と思われ、属人化している業務も、きちんと作業手順を洗い出せば実はそれほどマニュアル化は難しくありません。もちろん、判断が必要な部分には判断基準も明記しておきます。
動画マニュアルの活用
テレワーク導入に向けてマニュアル化した作業内容や、複数の人に伝えたい指示内容は、動画マニュアルにしてしまいましょう。
マニュアルといえば昔は紙ベースで配布する形式が一般的でしたが、近年では優れたインターネット回線や端末の普及により、効率的に業務手順を身につけられる動画マニュアルが普及しつつあります。
動画マニュアルには、紙ベースのテキストにはないさまざまなメリットがあります。特に離れた場所で働くテレワーカーに、具体的な業務手順を伝える手段としてはピッタリです。
【動画マニュアルならではのメリット】
- わざわざテキストを開かなくても、手元にあるスマホなどの端末でいつでも再生可能
- 遠くにいる相手でも情報が問題なく伝えられる
- 文字を読むのが苦手な人でも、動画の再生なら苦になりにくい
- 動きや音声、配置など、文字からだと伝わりにくい情報が、動画ならわかりやすく伝えられる
- わからないところは繰り返し再生できる
- 変更があれば動画を更新するだけで良い
- 印刷コストや差し替えの郵送コスト、手間がかからない
- 自分のペースで学習できる
- 曖昧な表現を避けて指示を出せる
動画マニュアルはクラウドストレージで共有したり、様々な動画共有サイトを使ったりすれば共有できますが、ユイコモンズの「UIshare」のような動画マニュアル配信に特化したプラットフォームサイトを利用すれば、動画マニュアルの視聴状況も詳しく把握できます。「マニュアルを渡したのに読んでない」ということになる心配はありません。必要に応じて、マニュアルの内容に対する理解度テストの実施も可能です。
一度、動画マニュアルを作成しておけば、何度スタッフが変わっても研修資料として活用できます。外部委託すると動画の作成自体に一定の費用がかかりますが、長い目で見れば紙ベースのテキストを何度も印刷するより、コスト負担が下がることも多いようです。
まとめ
テレワークを導入すれば妊娠中や育児中、介護中などの事情を抱えた優秀なスタッフが退職することなく活躍し続けてくれることが期待できます。部分的に在宅勤務を導入し、移動の負担を減らすこともできるでしょう。
業務の見える化ができれば、テレワークの導入はそれほど難しくありません。業務効率を上げるためにも、動画マニュアルを上手に活用して業務の見える化を図りましょう。
eラーニングの概要・種類について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
eラーニングシステム11選をわかりやすく比較!〜メリットやデメリットまでご紹介~

クラウド型動画eラーニングシステム
UIshare(ユーアイシェア)のサービス資料
圧倒的な低コスト、充実したサポート体制で、社員教育・社内情報共有・パートナーへの情報共有・動画 e ラーニング・eラーニング販売など様々なシーンでご利⽤いただけます。