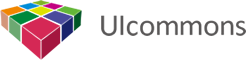教育機関や行政機関にとってナレッジやノウハウの蓄積や共有は重要な課題ですが、民間企業にとってもそれは同じこと。多くの人が何らかの組織に所属し活動する中で、ナレッジもノウハウも蓄積・共有しながら組織全体で活用していくことで、業務効率化や生産性向上につながります。
上記では「ナレッジやノウハウ」と一括りにしましたが、厳密にはナレッジとノウハウは別のものです。
本コラムでは、それぞれの違いを解説した上で、ナレッジやノウハウを蓄積すべき理由やメリットをご紹介いたします。
【関連記事】
ナレッジ共有とは? ~ナレッジ共有を上手く進めるためのポイント~
ナレッジ共有のメリットと成功させるポイント! おすすめのツールもご紹介
ナレッジとノウハウの違いとそれぞれの意味
ナレッジとノウハウは同じように使われることが多いですが、どのような違いがあるのでしょうか?以下で解説します。
ナレッジの意味
ナレッジ(knowledge)とは、日本語では「知識」「情報」などと訳されます。
ビジネスシーンにおいては、企業活動の中で得られた、自社にとって価値のある情報や経験、知見を指します。
社内に蓄積したナレッジを経営や部門の運営に活用することで、業務効率化を進めたり、生産性向上を測ったり、市場での競争力を強めたりします。
ノウハウの意味
一方、ノウハウとは、経験を積み重ねることで得られた専門的知識を意味する和製英語で、「know-how」と表記されます。どちらかというと「知識」や「情報」よりも「知恵」に近い意味合いで使われます。
ビジネスシーンに「ナレッジ」という言葉が使われる以前は、同じような意味で使われることもありましたが、ナレッジに比べると、たとえば、特定の業務や作業といった限定された狭い範囲で使われます。
ナレッジとノウハウの違いとは
ナレッジとノウハウの違いをまとめると、ノウハウが自社の社員の経験に基づいて培われた特定の業務などにおける知恵であるのに対し、ナレッジは必ずしも経験に基づいたものに限らず、自社に蓄積された経営や企業活動に利用できる価値ある情報、知見を広く指す言葉です。
わかりやすい例を挙げると、社員が参加したセミナーなどで学んだ内容も、自社に持ち帰ることでナレッジとして蓄積できます。しかし、これはノウハウではありません。
ナレッジの方が意味が広く、ノウハウを内包する概念だといえます。
ナレッジやノウハウを蓄積すべき理由
ここまでにも、ナレッジやノウハウを蓄積し活用する重要性はなんとなくお伝えしてきましたが、さらに具体的にご紹介します。
業務効率化を実現するため
社内にナレッジやノウハウを蓄積し、資料化(言語化・図示化)して共有すれば、これらの知識を直接得た社員以外のメンバーが、イチから情報収集したり経験したりするのにかかる時間と手間を省略でき、業務効率化につながります。身近な例では「マニュアル」が挙げられます。
このように、言語化されていない「暗黙知」の状態から明文化された「形式知」に変化させることで、蓄積・共有しやすくなります。
属人化を防ぐため
社員が業務を通して得た経験や、業務外で本などから学んだ知識は、その社員が業務に取り組む上で役に立ちます。会社としても、その社員がいる限り、生産性向上や競争力強化などのメリットを受け取れます。
しかし、個人の中にあるままだと、その社員が退職すればナレッジやノウハウも失われてしまいます。
もっといえば、その社員に聞けばわかる知識を得たい時に、会議中で聞けないから終わるのを待つ、といった非効率的なことも日常的に起きてしまうわけです。
そこで、企業の中にナレッジやノウハウとして蓄積しておけば、従業員が退職した時だけでなく、異動があったり新卒・中途で社員が入社したりした場合も、ナレッジやノウハウを活用しながら誰もが近しいレベルで業務を行えるようになります。
業務に不慣れな新入社員などが自力で問題を解決できる
新卒や中途で入社した経験の浅い社員は、研修などを通して会社や業務に慣れていくことになりますが、実際に現場に出てからでないとわからないこともたくさんあります。多くの場合は、教育係となる上司がいて、不明点はその都度、尋ねて解消することになりますが、上司が忙しそうだったり、すでに何度も質問していたりすると、気兼ねして聞きづらく感じる人もいるでしょう。
そんな時、社内のデータベースにナレッジやノウハウを集めた資料があれば、新入社員が検索して必要な情報にアクセスでき、自力で解決できる機会を増やせます。
まとめ
「ナレッジ」と「ノウハウ」は、よく混同して使われているのが散見されますが、厳密には異なる意味を持ち、ナレッジがノウハウを含む大きな概念となります。
ただ、どちらも蓄積・共有するメリットは大きいです。
これまで意識的にナレッジやノウハウを蓄積してこなかったという企業様は、まずは社員が個人で保有している形式知・暗黙知を収集するところから始めてみてはいかがでしょうか。

法人向オリジナル動画配信プラット フォーム
UIshareのサービス資料
動画配信プラットフォーム UIshareの総合サービス資料です。
特徴、機能、金額の詳細をこちらのサービス資料にまとめています。