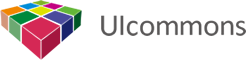以前から、オンラインによるセミナー開催は実施されてきましたが、新型コロナウイルス禍の影響で、ウェビナーが一気に市民権を得た感があります。
ウェビナーの存在を知りつつ、これまで実施してこなかった企業様の中にも「そろそろ、取り組んでみようか」とお考えのところがあるのではないでしょうか。
当メディアでも、これまでウェビナーに関するコラムを2点、公開しましたが、本コラムでは、これからウェビナー開催の検討を本格化させたいという企業様向けに、具体的なウェビナーの活用シーンとおすすめのツールをご紹介いたします。
【関連記事】
ウェビナーとは?―基礎知識とメリット・デメリット―
ウェビナーは1回開催して終わりではない-ウェビナー動画をリサイクルして有効活用!
ウェビナーの活用シーン
まずは、どのようなシーンでウェビナーを活用できるのかを押さえておきましょう。
セミナー・講義
企業であれば、見込客や既存顧客を対象として、ノウハウなどを共有するためのセミナーを、教育機関であれば生徒を対象とした商材としての講義と、オフラインのセミナーをそのままオンライン化するという活用方法です。
基本的に、講師と視聴者の人数比は「1:N」が想定され、事前に録画・編集しておいた講義を放映するタイプと、リアルタイムで講師が講義を行うタイプに2分できます。
講義自体は一方向性ですが、チャットや質疑応答時間を設けることで双方向性のコミュニケーションを実現できます。
使用するツールによっては、登録ユーザーが講義を視聴したかどうか(出席)をチェックすることも可能でます。
製品・サービスの説明会
見込客や顧客を対象に、自社の製品・サービスを詳しく説明するプロモーションにもウェビナーを活用できます。
製品・サービスの説明会でウェビナーを利用するメリットは、本来なら現地へ出向かないと見られないような場面(製造現場など)を、動画を使うことで簡単に共有できたり、3D画像やズーム機能を活用することで、オフラインのセミナーでは伝えづらい製品の詳細を伝えることができる点です。
参加者からの不明点も、チャット機能の活用や質疑応答時間を設けることで解消できます。
eラーニング
「セミナー・講義」とも似ていますが、こちらはオンデマンドを想定した教育・研修向けで、あらかじめ録画・編集しておいた動画教材を、ユーザーの都合に合わせて配信するというスタイルです。
ユーザーは個々のペースで学習できるため、学生の自習や社会人の研修、スキルアップなどの目的に向いています。
カスタマーサポート、カスタマーサクセス
既存顧客に対するカスタマーサポートやカスタマーサクセスでもウェビナーを活用できます。
あらかじめ、質問の多い内容を動画にまとめ、オンデマンド形式でいつでも必要な時に視聴できるように用意しておくほか、顧客ごとに担当者がリアルタイムでヘルプデスク対応するといった利用法もあります。
対面によるカスタマーサポート、カスタマーサクセスに比べて人件費を削減しつつ、電話によるサービスよりもわかりやすく質の高い内容を提供することが可能です。
採用説明会
企業などの採用説明会のオンライン開催にもウェビナーを活用できます。
特に、地方に居住している志望者も参加しやすいのがウェビナーのメリットです。
ツールによっては、志望者同士での懇親会なども開催できます。
説明会の開催後、エントリーシートのURLを共有すれば、そのままエントリーしてもらうことも可能です。
ウェビナーで使えるおすすめのツール
ウェビナー向けのツールもいろいろリリースされていて、機能もさまざまなものが揃っています。
ここでは、6つのツールをピックアップしてご紹介いたします。
Zoom Webinar(Zoomウェビナー)
Web会議システムで有名なZoomは、有料プランを契約すると、ウェビナー用アドオン「Zoomウェビナー」を契約できるようになります。
「Zoomウェビナー」は、最大接続人数によって料金プランが異なり、最大で1万人までの接続が可能(視聴のみの場合。双方向性の接続は100人まで)。プラン変更は月単位で柔軟に行えるようになっています。
Cocripo(コクリポ)
ウェビナー専用ツール「Cocripo(コクリポ)」は、接続の安定性を売りにしたツールです。
無料で使える「フリープラン」から用意されていますが、これは最大接続人数が3名までのため、あくまでもお試し利用にとどまりそう。有料プランは、月額3万円の「ビジネスプラン」(最大接続人数100名)からです。
V-CUBEセミナー
ウェビナーやオンデマンドコンテンツ配信を想定したWeb会議システム「V-CUBEセミナー」は、最大で1万拠点までにリアルタイム配信が可能なWeb会議システムです。対応言語も5ヵ国語対応なので、グローバルな配信に向いています。
サポート体制が充実しており、24時間365日対応してもらえます。
Cisco Webex Events
「Cisco Webex Events」は、世界最大のコンピュータネットワーク機器開発会社であるシスコシステムズが提供しているウェビナーツールです。
無料のプランも用意されていますが、使用時間は50分までで、機能もかなり制限されているので、あくまでもトライアル用と考えた方が良いでしょう。
有料プランの最大接続人数は、プランによって100~200名。
開催後の効果測定が行える機能が充実しており、アフターフォローにも注力しているため、ウェビナーから集客して顧客化する施策に活用できそうです。
Calling Webinar
「Calling Webinar」は、1,000人規模大規模イベントを想定したウェビナーツールで、Web会議ツール「Calling Meeting」の姉妹サービスです。ホスト・ゲスト間でのタイムラグの少なさを売りにしています。
ゲストもホストもアカウント、インストールとも不要で身軽に運用できるそうです。
リリースキャンペーンとして、2021年8月31日利用分まで無償提供中です。
UIshare
UIshareは、17万人に利用されている法人向けの動画配信サービスです。特に、e-ラーニングビジネスなど、教育分野に強みを持ち、「オンラインテスト」や「認定証」の機能などが付いています。
申し込み登録後、すぐに利用開始できるスピーディさも特長です。
利用料金は、月額1,000円(10ユーザーまで)からとリーズナブルで、無料トライアルも用意されています。
ウェビナーを開催する際のポイント
ウェビナーの開催内容とツールが決まれば、後は実施するだけです。あらかじめ、ポイントを押さえ、失敗を回避しましょう。
配信側・参加者とも通信環境を確認
ウェビナー開催では、配信するホスト側だけでなく、参加者側の通信環境も整っていなければスムーズな配信はできません。
ホスト側がもし、自社のインターネット回線が建物の共用回線である場合、セミナー中にほかに接続者が多いと速度が遅くなることがあるので、できれば専用回線を使用するのがベターです。
必要な帯域幅は、配信ツールや配信する映像の解像度などにもよりますので、仕様を確認しましょう。たとえば、Zoom Webinarなら、「1080pHDビデオ」をグループビデオ通話で配信するのに3.8Mbps/3.0Mbps(上り/下り)が推奨されています。
参考:「Windows、macOS、およびLinuxのシステム要件」zoomヘルプセンター
参加者側は、基本的に下りの帯域幅のみチェックすれば問題ないでしょう。同じくZoom Webinarでは、HDビデオの場合、1.2 Mbps(下り)が推奨されています。
ウェビナー用の周辺機器を用意
ウェビナーを開催するには、配信ツールのほかにカメラやマイクといった機材が必要になってきます。パソコンに内蔵されたカメラやマイクでは鮮明に伝えられないケースが多いので、できるだけ外付けのものを用意しましょう。
カメラは、高解像度のものがベターですが、配信ツールの上限を超えてまで高解像度にしても意味がないので、配信ツールのスぺックをチェックしましょう。
マイクは、講師が動く場合はヘッドセットタイプがおすすめです。講師が1名のみでパソコンの前に座ったままの場合はパソコン内蔵のWebカメラでも良いでしょう。
双方向性のコミュニケーションが取れる機能を活用
一方的なコミュニケーションでは、ウェビナー参加者が内容などに満足しているのか、それとも、わかりにいなどの不満を抱えているのかが見えてきません。
また、参加者もただ視聴しているだけだと、オフラインでの開催よりも飽きやすく、離脱してしまいかねません。
ウェビナーツールに「チャット」や「挙手」、「投票」といった機能が付いている場合は、積極的に活用しましょう。もし、ツール内に機能が付いていなければ、Sli.do(スライドゥ)など外部ツールを併用することで補います。
効果測定を実施
ウェビナーを開催したら、次回への改善へつなげるために必ず効果測定を実施しましょう。
指標としては、集客率や参加率、受注率、理解度・満足度などがあり、ウェビナーのツールからデータを取れるものもありますし、開催後にアンケート調査を実施して集計するなどの方法もあります。
まとめ
以上、ウェビナーの活用シーン、おすすめツール、開催の際のポイントをご紹介しました。
対面でのセミナーが難しい今、ウェビナーを導入する企業は確実に増えています。遅れを取らないためにも、少しでも早く取り組みをスタートした方が良いでしょう。
企業によって活用したい場面やツールに求める機能は異なってくると思いますので、本コラムなどを参考に、じっくりと検討してみてください。 ウェビナーをうまく活用して、新規顧客獲得などを目指しましょう。

法人向オリジナル動画配信プラット フォーム
UIshareのサービス資料
動画配信プラットフォーム UIshareの総合サービス資料です。
特徴、機能、金額の詳細をこちらのサービス資料にまとめています。